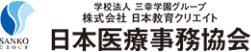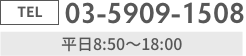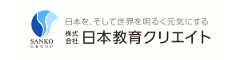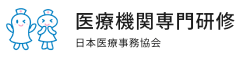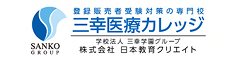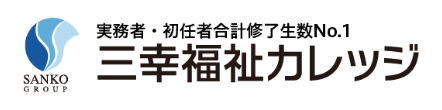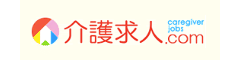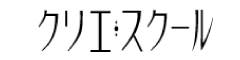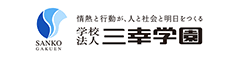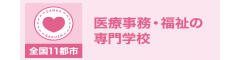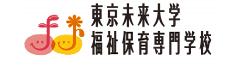- 医療事務の資格取得なら日本医療事務協会
- 講座⼀覧
- 医師事務作業補助者(ドクターアシストクラーク)とは
- 今、医療現場で求められている 「医師事務作業補助者」とは?|医師事務の資…
コラム

今、医療現場で求められている 「医師事務作業補助者」とは?|医師事務の資格講座なら日本医療事務協会
目次
医師事務作業補助者とは、文字通り「医師の事務作業をサポート(補助)する者」です。
忙しい医師に代わり、様々な「事務作業」を医師事務作業補助者が「代行する」「サポート(補助)する」ことにより、医師は「診療業務」に集中ができ、質の高い安定的な診療を提供することが可能になり、医療の質の向上つながると期待されています。また、待ち時間の短縮にもつながり、医療現場の円滑な運営には欠かせない存在として、今、医療現場で求められている「医師事務作業補助者」という職種があります。
医師の「もう一人の手」医師事務作業補助者の役割
限られた診療時間の中、医師は、患者の話を聞きながらパソコンを入力し、次々と指示を出し、いつも忙しく時間に追われているように見えませんか?
医師の業務は、患者を診察・治療する「診療行為」と診療行為に伴って発生する「事務作業」があります。
「事務作業」には、法律で定められたカルテの記載以外に、診断書の作成、紹介状の作成、意見書の作成、各種保険の証明書の作成、患者や家族への説明資料の作成といった文書作成の業務があります。また、医療のIT化が推進され、「診療行為」と並行してのカルテ入力があり、医師の負担は年々大きくなっています。
「医師事務作業補助者」という職種の誕生
2008年度診療報酬改定で「勤務医の負担軽減」を目的に創設された「医師事務作業補助体制加算」により、「医師事務作業補助者」という職種が誕生しました。2020年度診療報酬改定では、対象病床の範囲が拡大され、診療所やクリニックなど規模の小さな医療機関でも入院用のベッドがあれば、「医師事務作業補助体制加算」の対象となりました。2024年度診療報酬改定で、さらに点数の引き上げが行われ、「医師事務作業補助者」の存在は、勤務医の負担軽減に高い効果があると評価されてきています。
「経営面での役割」医師事務作業補助体制加算の算定
「医師事務作業補助者」を配置する医療機関では、専用の作業スペースや、 重要な情報を管理するシステムなどの体制等を整備し、維持することで、患者さまより「医師事務作業補助者体制加算」を入院初日に算定することができ、「医師事務作業補助者」は、経営面でも貢献する存在でもあります。
「医師の働き方改革」による「医師のタスクシフト先」として期待
日本はいつでも、どこでも必要に応じて医療が受けられる環境にありますが、その環境は医師の長時間労働などにより支えられています。2024年4月から「医師の働き方改革」が始まり、医師でなくてもできる作業のタスクシフト(ある職種が担っていた業務の一部を他の職種に移管すること)先として「医師事務作業補助者」が期待されています。
医師が「事務作業」に追われる時間を減らすことで、患者と向き合う時間を増やすことができ、満足度の高い医療の提供につながっていきます。そういった医療の質を支える重要な役割を「医師事務作業補助者」は担っているのです。
「縁の下の力持ち」医師事務作業補助者の仕事
「医師事務作業補助体制加算」届出の対象となっている医師事務作業補助者の業務内容は、施設基準によって以下のように定められています。
医師事務作業補助者の業務は、医師(歯科医師を含む)の指示の下に、
・診断書等の文書作成補助
・診療記録への代行入力
・医療の質の向上に資する事務作業
(診療に関するデータ整理、院内がん登録等の統計・調査、医師の教育や研修・カンファレンスのための準備作業等)
・入院時の案内等の病棟における患者対応業務及び行政上の業務
(救急医療情報システムへの入力、感染症サーベイランス事業に係る入力等)への対応に限定する。
(令和6年保医発0305・4)
診断書、他の医療機関への紹介状、意見書や各種保険の証明書の作成などの「診断書等の文書作成補助」、電子カルテへの診療内容入力、処方箋の作成や診察・検査予約などの「診療記録への代行入力」、学会・会議・カンファレンスで使用する資料の作成、研究データのまとめ、国が取りまとめている「がん登録」、外科領域(NCD)のデータベースの作成等、医師の学術活動や研究のサポートの「医療の質の向上に資する事務作業」、感染症発生時の都道府県への届け出、救急医療情報システムへの情報入力の「入院時の案内等の病棟における患者対応業務及び行政上の業務」で、医療機関によって任される業務に違いがありますが、未来の医療にも貢献できる仕事内容です。
医療事務と医師事務の違い
医療事務は、受付や会計などの患者対応と医療費の算定を主な仕事とします。一方、医師事務作業補助者は医師の事務作業を代行する、サポートする仕事で、医療事務よりも、医師をはじめ看護師や検査技師など、さまざまな職員との関わりが深いのが特徴です。どちらも医療機関での事務職ですが、仕事の内容は全く異なります。
医療事務の業務には、受付、外来クラーク、病棟クラーク、入退院受付、会計、請求業務、病歴管理などがあります。このような業務を行っていた医療事務員が、「医師事務作業補助者」として配置されることがありますが、以下に示す医師以外の職種の指示の下に行われる業務は「医師事務作業補助者」の業務としないと定められています。
医師以外の職種の指示の下に行われる業務(「医師事務作業補助者」の業務としない業務)
・診療報酬の請求事務(DPCのコーディングに係る業務を含む)
・窓口・受付業務
・医療機関の経営
・運営のためのデータ収集業務
・看護業務の補助及び物品運搬業務等について
(令和6年保医発0305・4)
「あなたのおかげで」医師事務作業補助者のやりがい・魅力

医療に近い現場で仕事をしたい人、正確な事務作業・丁寧な仕事が得意な人、パソコンが得意な人が、医師事務作業補助者に向いている人とされています。医師と患者をつなぐ架け橋となり、人を支えることにやりがいを感じることができる仕事です。「あなたがいてくれるおかげで、患者と目を合わせて話す時間が増えました。診療に集中することができます。」そんな言葉を医師からもらえるかもしれません。
32時間基礎知識研修を受けるなら「日本医療事務協会」
医師事務作業補助者体制加算を算定するためには、医師事務作業補助者を配置してから、入職後6ヶ月間を研修期間とし、その6ヶ月の研修期間内に医師事務作業補助者としての業務を行いながら、32時間以上の業務内容に必要な研修を実施することが必要とされています。研修内容は「基礎知識」として以下のように定められています。
基礎知識
・医師法、医療法、医薬品医療機器等法、健康保険法等の関連法規の概要
・個人情報の保護に関する事項
・医療機関で提供される一般的な医療内容及び各配置部門における医療内容や用語等
・診療録等の記載・管理及び代筆、代行入力
・電子カルテシステム(オーダリングシステムを含む)
日本医療事務協会の「医師事務作業補助者養成通信講座(ドクターアシストクラーク)」では、
「試験はなく、講座修了時に修了証を発行」
就職するタイミングで必ず研修を修了している必要はありませんが、この修了証が医師事務作業補助者に必要な32時間基礎研修を受講した「証」になり、履歴書にも記入できる効力のあるものになります。別途、試験を受ける必要はありません。
「現場を意識した実践的な教材で初学者でも安心」
病院で働く上での心構え、現場で必要な医学知識、診療録の書き方まで、実践的な内容でこれから医療現場で働く方は、就業前の学びはもちろん、就業後にも役立つ教材で学習することができます。
「学習コンプリート動画でサクサク学習」
テキストを完全網羅した学習コンプリート動画で講師がわかりやすく解説しているので、通信講座でも安心して学べます。課題は専用webページで解答でき、すぐに解説も確認できるのでご自身の習熟度がすぐ確認できます。有効期間が1年間あるので、修了後も現場での疑問や不安の解消などに長くお使いいただけます。
医師事務作業補助者講座(ドクターアシストクラーク)

- この記事の監修者
- 日本医療事務協会 編集部
日本医療事務協会は1975年の設立以来、医療・介護業界の事務職を育成する専門校として、数多くの受講生を現場へと送り出してきました。
「仕事のやりがいも充実したプライベートもあきらめない」そんなチャレンジに寄り添うため、現場の声を最大限に取り入れた「実務直結のカリキュラム」と、高い合格率を支える「手厚いサポート制度」をご提供しています。